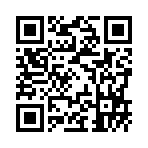2012年01月14日
どんど焼き(1/14)
(1/14・土)
、左義長(三毬杖・さぎちょう)という小正月に昔の宮中で行われた火祭りの行事が民間行事になったもので、もともと吉書を焼く儀式でしたが、お正月のお飾りを焼くようになりました。
1月14日の夜または1月15日の朝に、刈り取り跡の残る田などに長い竹を3、4本組んで立て、そこにその年飾った門松や注連飾り、書き初めで書いた物を持ち寄って焼きます。その火で焼いた餅(三色団子の場合もある)を食べたり、注連飾りなどの灰を持ち帰り自宅の周囲にまくと、その年の病を除くとも言われています。また、書き初めを焼いた時に炎が高く上がると字が上達すると言われています。
民俗学的な見地からは、門松や注連飾りによって出迎えた歳神を、それらを焼くことによって炎と共に見送る意味があるとされています。お盆にも火を燃やす習俗がありますが、こちらは先祖の霊を迎えたり、そののち送り出す民間習俗が仏教と混合したものと考えられています。
どんど、どんど焼き、とんど(歳徳)焼き、どんと焼きとも言われますが、歳徳神を祭る慣わしが主体であった地域ではそう呼ばれ、出雲方面の風習が発祥であろうと考えられています。とんどを爆竹と当てて記述する文献もあるそうです。これは燃やす際に青竹が爆ぜることからつけられた当て字であろうと考えられています。
子供の祭りとされ、注連飾りなどの回収や組み立てなどを子供が行う事も多いそうです。また、小学校などでの子供会(町内会に相当)の行事として、地区ごとに開催される事もあるそうです。地方によって、焼かれるものの違いもあるそうです。




、左義長(三毬杖・さぎちょう)という小正月に昔の宮中で行われた火祭りの行事が民間行事になったもので、もともと吉書を焼く儀式でしたが、お正月のお飾りを焼くようになりました。
1月14日の夜または1月15日の朝に、刈り取り跡の残る田などに長い竹を3、4本組んで立て、そこにその年飾った門松や注連飾り、書き初めで書いた物を持ち寄って焼きます。その火で焼いた餅(三色団子の場合もある)を食べたり、注連飾りなどの灰を持ち帰り自宅の周囲にまくと、その年の病を除くとも言われています。また、書き初めを焼いた時に炎が高く上がると字が上達すると言われています。
民俗学的な見地からは、門松や注連飾りによって出迎えた歳神を、それらを焼くことによって炎と共に見送る意味があるとされています。お盆にも火を燃やす習俗がありますが、こちらは先祖の霊を迎えたり、そののち送り出す民間習俗が仏教と混合したものと考えられています。
どんど、どんど焼き、とんど(歳徳)焼き、どんと焼きとも言われますが、歳徳神を祭る慣わしが主体であった地域ではそう呼ばれ、出雲方面の風習が発祥であろうと考えられています。とんどを爆竹と当てて記述する文献もあるそうです。これは燃やす際に青竹が爆ぜることからつけられた当て字であろうと考えられています。
子供の祭りとされ、注連飾りなどの回収や組み立てなどを子供が行う事も多いそうです。また、小学校などでの子供会(町内会に相当)の行事として、地区ごとに開催される事もあるそうです。地方によって、焼かれるものの違いもあるそうです。
作成者:Sato




Posted by Rokuty
at 08:32
│Comments(0)